前回は主に企画書の要素とその構成について解説しました。
しかし、いざ企画書を書こうとしても、面白いアイデアが思いつかずに悩んでしまうことも少なくないと思います。
今回は、企画書の方向性から、オリジナリティのあるゲームのアイデアの出し方まで、これからゲーム業界を目指す方にも役立つよう、わかりやすく解説していきます。
ぜひ最後までお付き合いください!
企画書の用途で変わる必要なアイデア
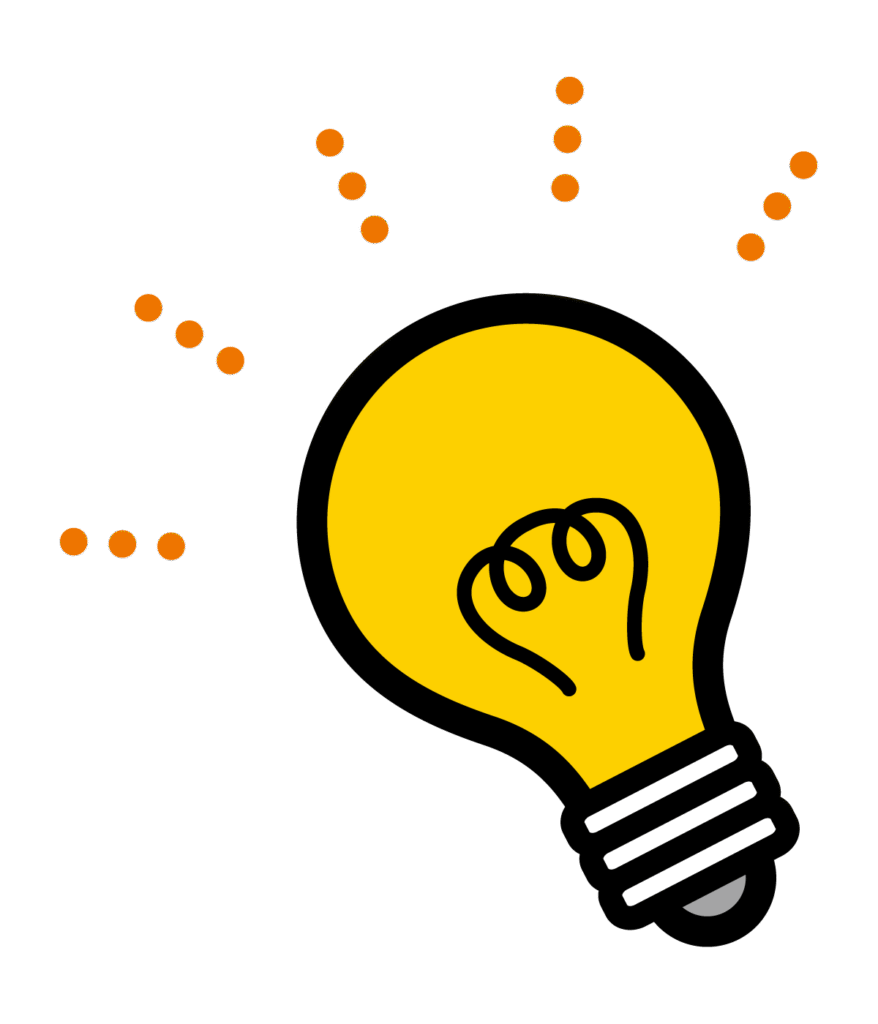
どんな企画書を書くにも、その企画書が魅力的であることは絶対条件です。
しかし、企画書が何に使われるかで、アイデアの出し方は変わります。
「自主制作ゲームの企画書」「面接用の資料としての企画書」「会社の業務に使う企画書」など、用途に適したアイデアの考え方があるのです。
まずはあなたが書こうとする企画書の用途から、適したアイデアの方向性を整理してみましょう。
自主制作ゲームの企画書
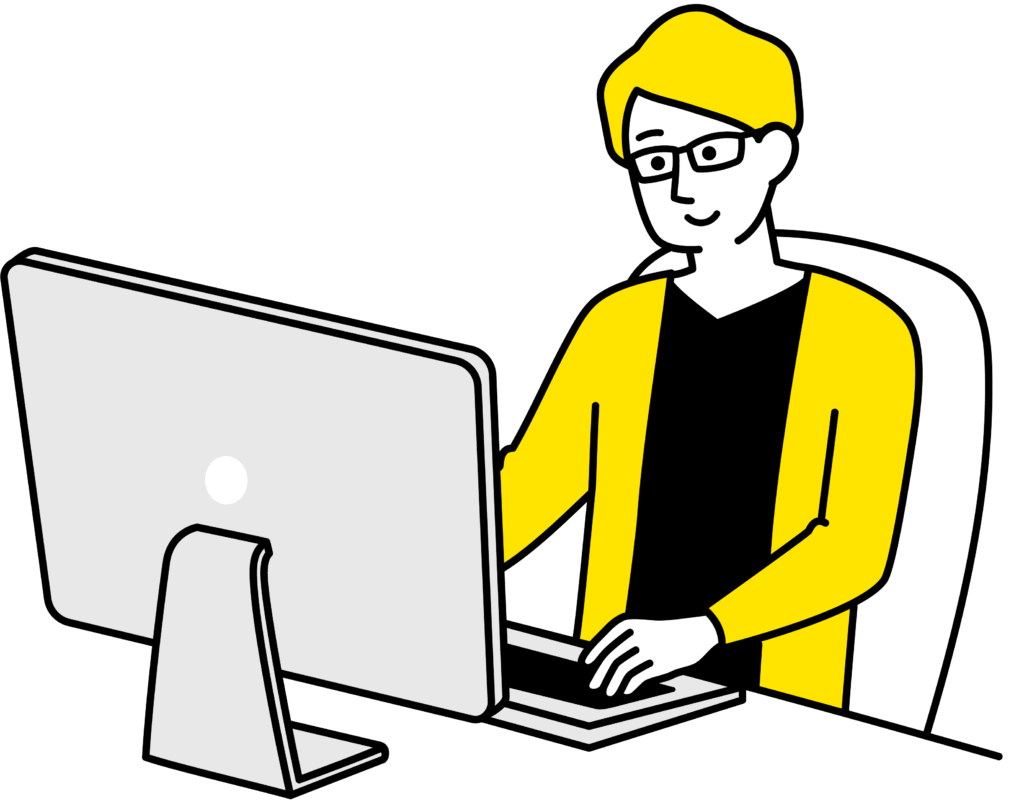
- どういった書類なのか?
- 仲間や支援者を集めたり、モチベーションを維持したりするための土台となる書類。
- 題材の選定:
- 個人のスキルや予算に合わせて、本当に自分が作りたいものを選定できます。自由度が高く、個性的なアイデアを盛り込みやすいのが特徴です。
- アイデアの方向性
- 「誰も見たことがない、面白いゲームを作りたい」という、あなたの熱意や個性を表現するアイデアを重視します。
面接用の資料としての企画書
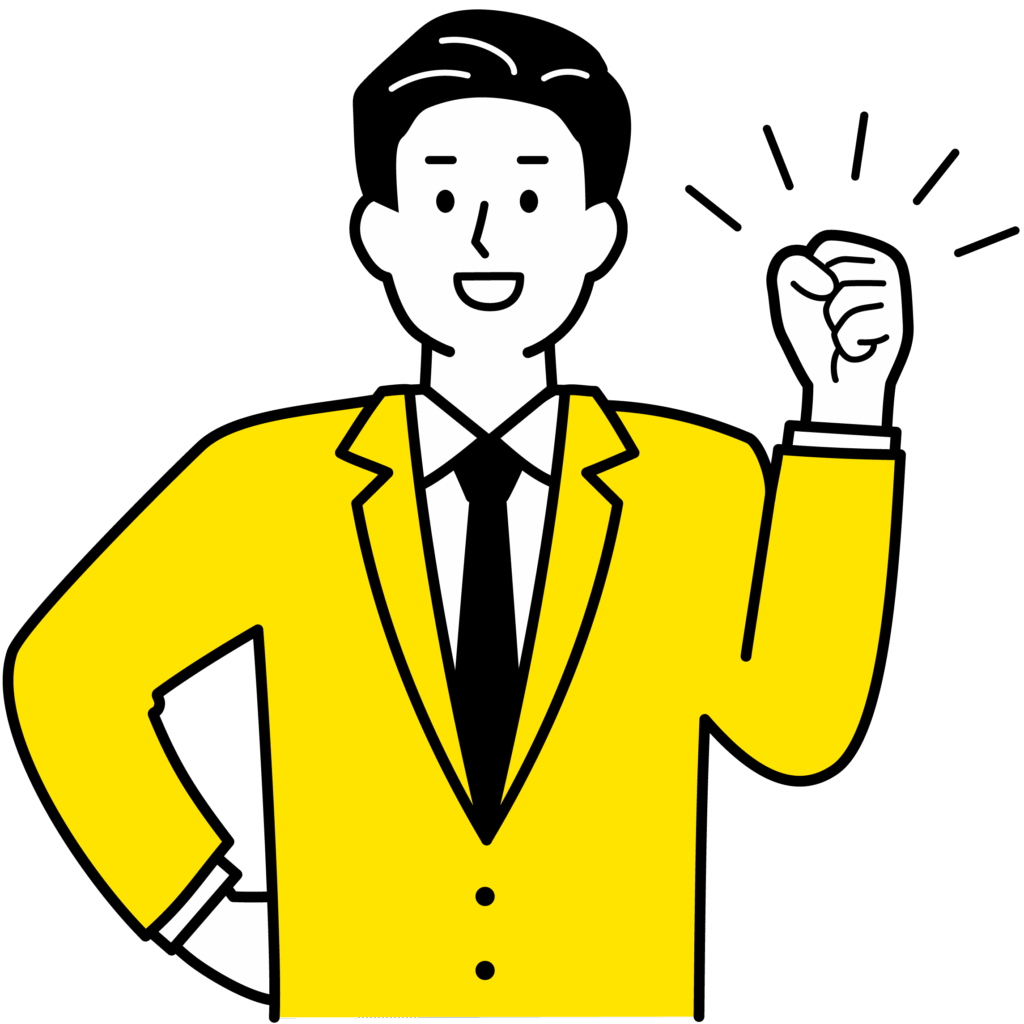
- どういった書類なのか?
- あなたのゲーム制作に対する適性や能力をアピールするための書類。
- 題材の選定
- 企業が手掛けているジャンルや、市場で流行しているジャンルなど、面接を受ける会社や時代背景を考慮した題材が好まれます。
- アイデアの方向性
- 企業の方向性や市場のニーズを理解していることを示しつつ、「自分らしさ」や「独創性」を表現できるようなアイデアを盛り込むことが重要です。
会社の業務に使う企画書
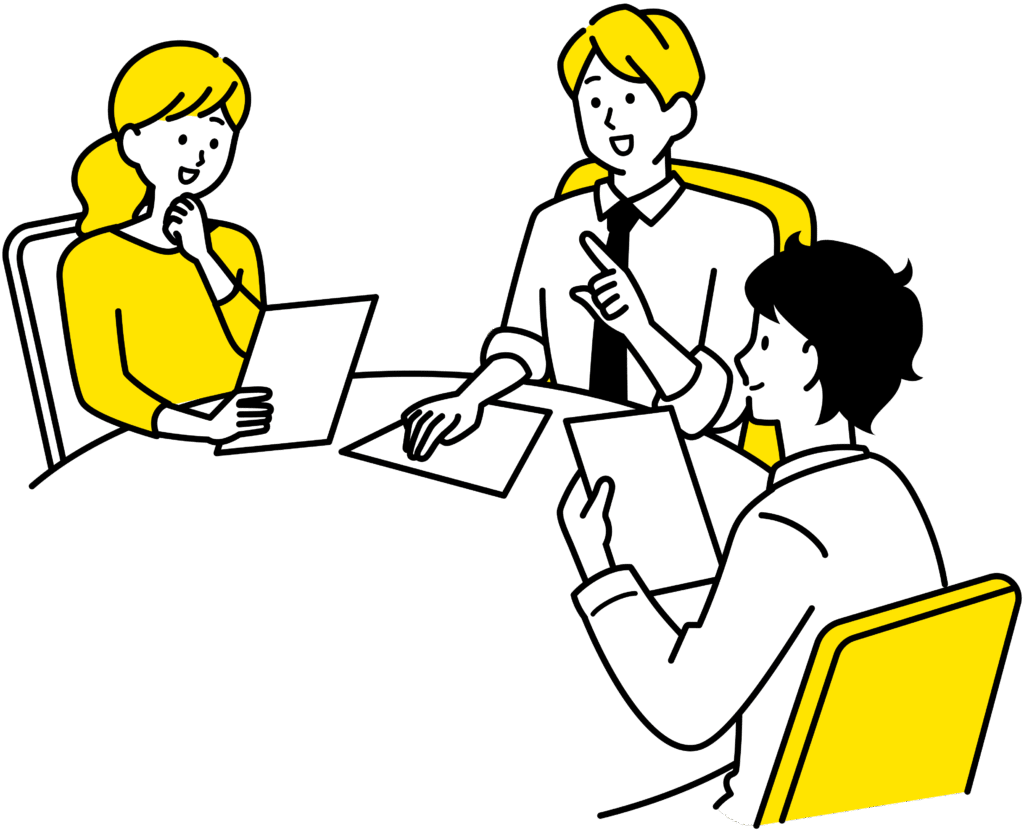
- どういった書類なのか?
- 会社の予算や人員、スケジュールを動かすための、実現可能性や収益性を重視した書類。
- 題材の選定
- 会社のIP(知的財産)や特定のジャンル、ターゲット層など、既に方向性が決まっているケースがほとんどです。
- アイデアの方向性
- 多くは、既に決まっている方向性の中で、他社製品との差別化を図ったり、ゲームの魅力を高めたりするための具体的なアイデアを盛り込むことが求められます。
このように、ゲーム企画書のアイデアを出すときは、企画書の用途に応じた考え方が大切になってきます。
しかし、方向性が決まった後は、その方向性で魅力的なアイデアが盛り込まれた企画書を書くことには何ら違いはありません。
業務で使われる企画書は、題材からジャンル、ゲーム性まで確定しているケースが多いので、そこから他との差別化や魅力を盛り込みますが、それ以外の企画書は、用途ごとに最適な方向性でまとめることになります。
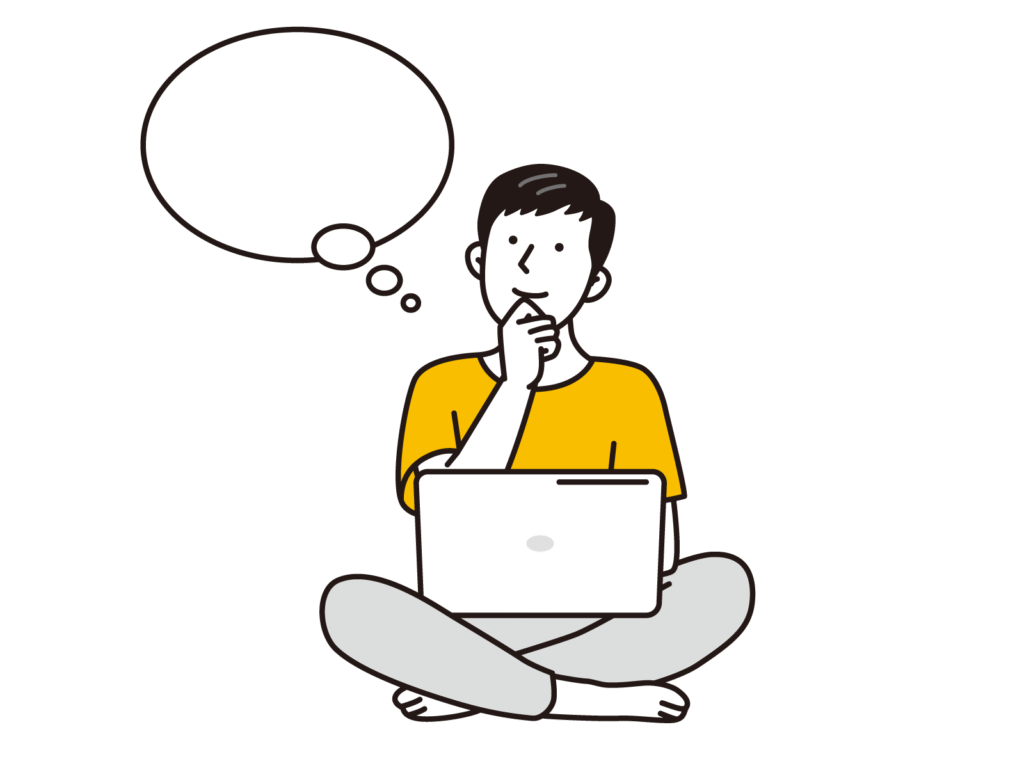
全てのジャンルに共通するオリジナリティーの生み出し方
あなたが「このジャンルのゲームの企画書を書こう!」と決めたとします。
そのジャンルが、よほど珍しいものでない限り、既に同じジャンルのゲームは市場に並んでいます。
一つのタイトルにのめり込まなくとも、どんなライバルがいるかのリサーチは必要です。
そして、ライバルの良いところをしっかりと分析しましょう。
そのうえで、市場にはないオリジナルのアイデアを盛り込んだ、魅力的な企画書を目指すのが最初の入り口です。
オリジナリティーを生み出すステップ
- リサーチ
- 企画しようとしているジャンルの市場調査をする。
- 分析
- 競合タイトルの良い点や成功している点を深く分析する。
- アイデア出し
- 市場にない、独自のアイデアを考える。
- オリジナルアイデアの完成
- 考えたアイデアを練り上げ、自分が納得できるレベルのアイデアとして完成させる。

オリジナリティーを「売り」と考える
オリジナリティーと一言でいっても、些細な見せ方や、他と違って見えないものでは、そうとは言えません。
企画書を見る者は、どんな立場の人間であっても、見たことのない新しいアイデアが書かれていれば、その企画書を評価しないわけにはいきません。
新しいアイデアとは、人の気持ちを大きく動かす「ゲームの売り」なのです。
新たな「売り」があることで、あなたの企画書は独自性に溢れ、人の目を引く魅力的なものになります。
売りは最低『10個』
このゲームにしかない「売り」を最低でも10個考えましょう。
あなたが書こうとしているジャンルのゲームで、これまでになかった、わかりやすくて面白いアイデアを考えます。
このアイデアを考えるときには、常識にとらわれず、とにかくたくさんのアイデアを書き出すことです。
企画書にまとめるときには最低10個の売りを目指しますが、アイデア出しの段階ではそれにとらわれず、どんどん出してみましょう。
※ちなみにこのステップは、オリジナリティーを生み出すステップの「3」にあたります。
売りになるアイデアの出し方
企画書に盛り込むアイデアは、分かりやすくなくてはいけません。
例えば、売りを数字で打ち出す場合。
- 作品A:・・使える武器が4種類
- 新企画・・使える武器が10種類!
- 作品B・・ステージ数が8個
- 新企画・・ステージ数が20個!
- 作品C・・操作できるキャラクターが6人
- 新企画・・操作できるキャラクターが15人!
- 作品D・・ストーリーの分岐が3つ
- 新企画・・ストーリーの分岐が10個!
数字は明らかな差が分かるので伝わりやすいのですが、次のように新しい遊び方を考えるのも有効な手段です。
- 作品E・・弾幕を避けるのが主流
- 新企画・・弾幕を吸収して攻撃ができる!
- 作品F・・敵を倒すのが主流
- 新企画・・敵を味方にして一緒に戦うことができる!
- 作品G・・ターン制バトルが主流
- 新企画・・行動順を自分でカスタマイズできる!
- 作品H・・装備は店で買うのが主流
- 新企画・・敵を倒して素材を奪い、好きな装備を作ることができる!
このように、すぐに思いつくレベルのアイデアでも構わずたくさん書き出しましょう。
完璧なアイデアを一発で出せる人間などこの世に存在しません。
最初は一見関係なさそうなAというアイデアが、Gというアイデアと混ざり合って、革新的な遊びが生まれる場合もあるのです。
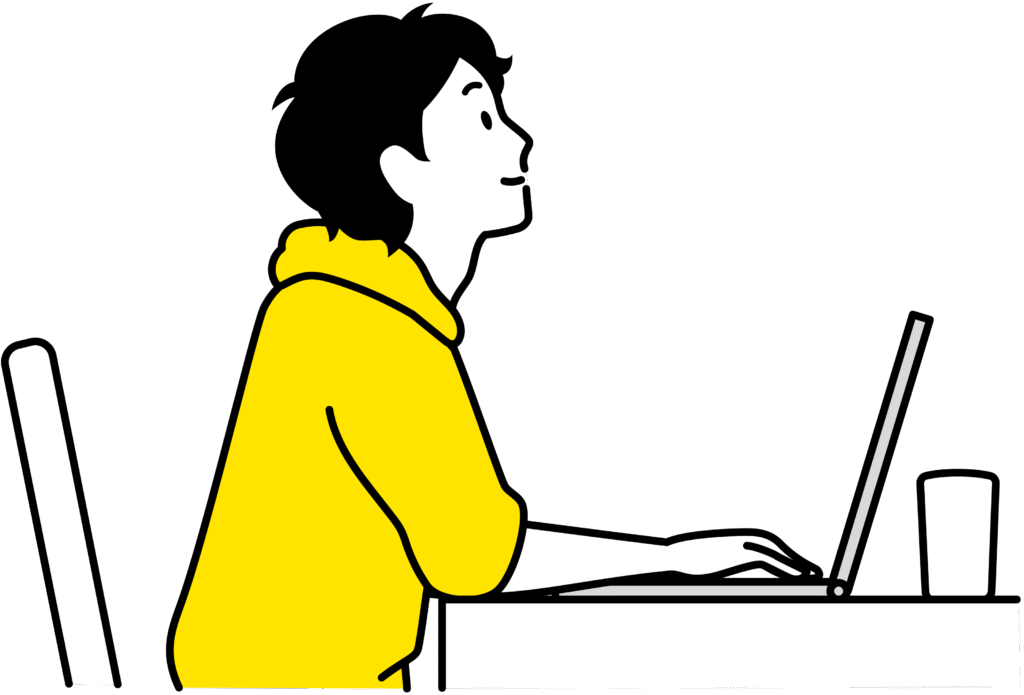
アイデアを出すのは難しくない
「アイデアを出す」と聞くと、何か特別な才能やひらめきが必要だと思うかもしれません。
しかし、それは大きな勘違いです。
アイデアとは、ゼロから生み出すものではなく、既存の要素を組み合わせたり、視点を変えたりすることで生まれるものです。
大切なのは、「常識にとらわれないこと」と「量を出すこと」。
多くの人は、「こんなアイデアは実現できないだろう」「これは面白くないだろう」と自分で勝手に判断して、頭の中に留めてしまいます。
しかし、最初の段階では、どんなに荒唐無稽なアイデアでも書き出すことが重要です。
そうやって書き出したアイデアを、後から現実的なものに落とし込んだり、他のアイデアと組み合わせたりすることで、唯一無二の「売り」が生まれます。
アイデアは、才能ではなく、訓練によって磨かれるスキルです。
日々、面白いと思ったゲームや映画、本、漫画などから、「なぜ面白いのか」「どうしたらもっと面白くなるか」を分析する習慣をつけることで、自然とアイデアを生み出す力が身についていきます。
まとめ
いかがでしたか?
今回は、企画書に盛り込むアイデアの出し方について解説しました。
企画書の用途は様々でも、企画の「売り」となるアイデアの出し方は共通しており、それは他にない新しい「売り」を、研究と試行錯誤の末に生み出すことです。
しかし、これは難しいことではありません。
日々の生活の中でアンテナを張り、積極的にインプットと分析を繰り返すことで、自然とユニークなアイデアが湧いてくるようになります。
大切なのは、日頃の習慣とあなたの実行力です。
もし、企画書にしたいゲームのイメージがある程度固まっているのであれば、前回の企画書の構成と今回のアイデア(売り)の出し方を参考に、用途に合った企画書を書き始めてみてはいかがでしょうか?
-scaled.png)

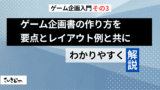


このステップを用いる以外に、一つ確実に言えることがあります。
それは、画期的なアイデアが必ずしも深い思考や努力の後に生まれるわけではないということです。
日常生活の何気ない瞬間にふとひらめき、それがとてつもなく優れたアイデアであることも十分に考えられます。
しかし、そうしたひらめきは意図して得られるものではありません。
そのため、アイデア出しに慣れていない人は、決まったステップに沿ってオリジナルのアイデアを生み出す訓練をすることをおすすめします。